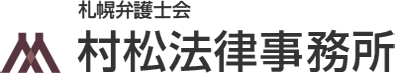【企業法務コラム】「経営者には、退職代行への対抗手段はないんでしょうか?」(元札幌地裁裁判官・労働審判官 内田健太)
弁護士の内田です(自己紹介はこちらをご参照ください。)
1 退職代行サービスの功罪
近年、退職代行サービスの利用者が増加しています。
前提として、私自身は退職代行サービスには、有益な面があると考えています。
実際問題、苛烈な労働環境に置かれている労働者の方は多く、
「辞めたいけど、辞めるといったら何を言われるかわからない」
という深刻な悩みを抱えている方にとって、労働者に代わり退職意思を示し、精神的苦痛・負担から解放させるという退職代行サービスは必要だと思います。
もっとも、近時、顧問先企業の皆様を中心に
「欠勤当日に退職代行サービスから連絡がきた。」
「引継ぎもなくいきなり辞められて困っている。」
「重要な資格を持つ従業員が突如辞めたため業務に多大な支障が出た。」
といったような相談も受けております。
「経営者は、退職代行サービスを無抵抗で受け入れるしかないのか?」
という点について少し考えてみたいと思います。
2 一般的な対応
労働法の教科書を読むと、
①労働者の退職は権利であり、2週間前に通知をすれば足りる
②労働者の有給取得も権利である
③使用者には有給行使に対して行使時期を変更する権利(時季変更権)があるが、退職時 期が決まっている場合には、他に変更先として提案できる時期がない以上、時季変更権 は行使できない
という趣旨の記載があります。
これらを併せると、労働者には、
「労働者には退職する権利がある。14日後に退職する。今日から退職までは有給を行使 するので出勤しない。有給取得分を含め、未払いとなっている賃料全額を支払え。」
と請求する権利が常にありそうにも見えます。実際、退職代行業者を通じてそのような請求を受けるケースは少なくありません。
現在の実務を見ても、上記の解釈の下、退職代行を素直に受け入れているケースが大半かと思います。
3 対抗策(対応方針)
原則論は上記のとおりだとして、使用者は、常にすべての要求に応じなければならないのでしょうか?
確かに退職は権利ですが、法律上、権利であっても、その行使方法、目的によっては権利行使が違法になることがあります(権利の濫用)。
いくら退職が権利だとはいえ、その行使には限度があるというべきでしょう。退職に至る経緯、退職の方法、その後の対応によっては、退職が違法なものとして損害賠償請求の対象になる場合もあると考えます。
実際に、裁判例にも、適切な引継ぎを行わずに従業員が失踪したという事案において、会社から従業員に対する損害賠償を認めたものがあります(知財高裁平成29年9月13日判決・判例秘書搭載)。
同裁判例が「雇用契約において,労働者は,使用者に対し,上記労務提供義務に付随して,当該労務の提供を誠実に行い,使用者の正当な利益を不当に侵害してはならない義務を負う」と指摘する点については、個人的にも全く異論がありません。
どのような退職が違法になるかは、➀会社側にハラスメント、労働基準法違反等の落ち度があったかどうか、➁退職の時期がいつ示されたか、③退職した者の職務は他の従業員で代替可能か、④引継ぎのない退職によりどの程度具体的な支障が生じるかといった点を総合的に考慮して判断することになると考えられます。
ご相談いただいた場合には、上記のような事情を中心に実情をお伺いした上、法的な見通しを踏まえ、退職代行への対応方針を検討して行くことになります。
はじめての方でもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
お悩みや問題の解決のために、私たちが力になります。折れそうになった心を1本の電話が支えることがあります。
10名以上の弁護士と専門家のネットワークがあなたの問題解決をお手伝いします。まずはお気軽にお問い合わせください。