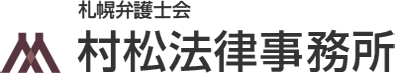【経営者向けコラム】「経営者の離婚はなぜ紛争化しやすいのか?」(元札幌地裁裁判官・労働審判官 内田健太)

1 経営者離婚の難しさ
離婚という問題は、誰しもが直面する可能性のある悩みです。
その上で、私の経験上、経営者の皆様の離婚については、紛争が深刻化しやすい傾向が顕著です。
私自身、家庭裁判所で裁判官として勤務していた際には、この問題の解決に関して沢山悩みました。
また、弁護士になった後も、経営者の皆様から、離婚に関する深刻なご相談を受けるケースが少なくありません。
そこで、改めて
「経営者の離婚はなぜ難しいのか?」
といった点についてお話したいと思います。
経営者の離婚において、特に問題となりやすいのが
「婚姻費用の金額」
「財産分与の決め方」
です。
2 婚姻費用
婚姻費用とは、主に別居時の夫婦間において、夫婦間の扶養義務に基づいて収入が多い方が少ない方に支払う金銭です。
婚姻費用の金額は、双方の収入額、子の数や年齢を基に、裁判所においても公表されている「算定表」に沿って決まれるケースが大半です。
もっとも、経営者の皆様の中には、平均年収に比べて多額の報酬をもらっている方も少なくありません。算定表は、年収2000万円を上限としておりますので、同金額を超える場合には算定表を利用することはできません。また、算定表の基礎にある考え方を機械的に当てはめると、婚姻費用が極めて高額になることが少なくありません。
そのため
「扶養の義務があるとはいえ、生活に必要な金銭には限りがある。いくら収入が高いとはいえ、月額100万円を超えるような高額金額を支払うのはやりすぎではないか?」
という疑問を持たれる方が少なくありません。
そのため、婚姻費用の金額について、争いが生じるケースが増えてきます。
3 財産分与
財産分与とは、夫婦の離婚時に、婚姻中に増加した共有財産を分配するための手続きです。婚姻開始時から別居までに増加した財産を、2分の1ずつ均等に分割するケースが大半です。
⑴ 問題点①財産分与の割合~2分の1ルールを適用するべきか?~
もっとも、夫婦の一方が経営者の場合、財産の増加額が極めて多額になるケースが少なくありません。夫婦の協力関係が財産の増加に貢献しているとしても、経営者の方の個人的な才能・努力が財産増加に寄与した側面が圧倒的に大きい場合には、2分の1という分配割合を維持することに疑問を持つ方が現れるのは自然な考えです。
「自分の多大な努力・労力により財産を増やしたのに、半分持っていかれるのは納得いかない」
と考えるのも十分に理解できる心情です。
経営者の離婚の場合には、財産をどのような比率で分けるのが適切かという分与割合を巡った紛争が先鋭化するケースが多いです。
⑵ 問題点②自社株の評価~自社株をいくらと評価するべきか?~
もう一つ問題になりやすいのが、「自社の株式をどのように評価するか」という点です。
日本の会社の約99%が、株式の譲渡について制限を設けている会社であり、自社株を換価することは現実的には困難です。
それでも、債務超過状態の会社を除けば、法律上は一定の価値がある財産として取り扱われます。
そのため、相手方からは、
簿価純資産ベースでの株価評価を主張してきたのに対し、
「簿価上はそれなりの株価が付いているが、実際の株式の価値はそんなに高くない。簿価で判断するのは不相当だ。」
といった形で、紛争が深刻化するケースが少なくありません。
また、特に深刻なのが、別居後相当期間が経過しており、別居から離婚までの間に、自社が成長し、株価も上昇したケースです。
このような場合、相手方からは
「自社株の評価は離婚時(現在)価格で評価するべき」
という主張が出されることが通例です。
もっとも、別居後の株価の上昇は経営者の方本人の努力によるものであり、夫婦の協力により生じたものではありません。
そのため
「別居後の株価上昇分を相手に支払う義務はない。株価は別居時を基準に判断するべきだ」
という形で、紛争が一層深刻になっていきます。
4 最後に
以上のように、経営者の方が離婚をする場合には、通常のルールを機械的に当てはめると、経営者にとって不平等な結果になるケースが少なくありません。そのため、
①婚姻費用の決め方
②財産分与の決め方(分与の割合、自社株の評価)
という場面で、問題が深刻化しやすいのが現状です。
このようなケースで、経営者の実情・特徴を無視して、通常の原則ルールを機械的にあてはめると、不当な結論になることが多く、依頼者にとって納得のいく解決を迎えることが極めて困難になります。
私としては、このようなケースでは、できる限り実情に沿った結論に近づけるよう、安易に前例を踏襲することなく、粘り強い訴訟活動を心がけております。
はじめての方でもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
お悩みや問題の解決のために、私たちが力になります。折れそうになった心を1本の電話が支えることがあります。
10名以上の弁護士と専門家のネットワークがあなたの問題解決をお手伝いします。まずはお気軽にお問い合わせください。